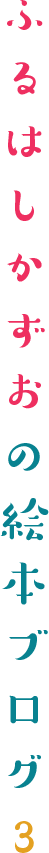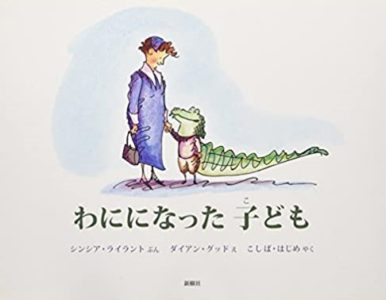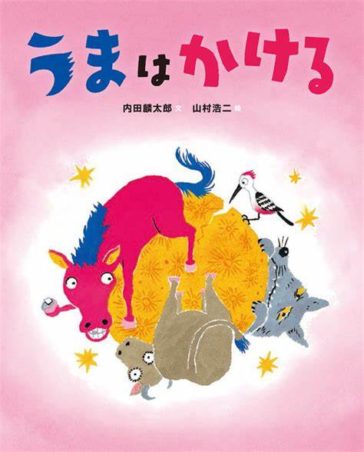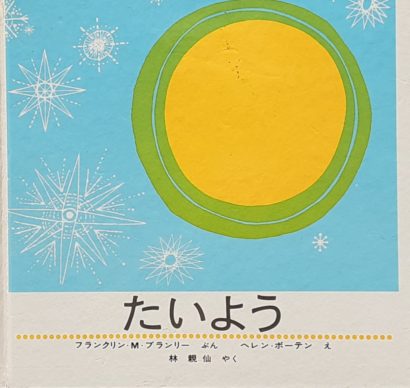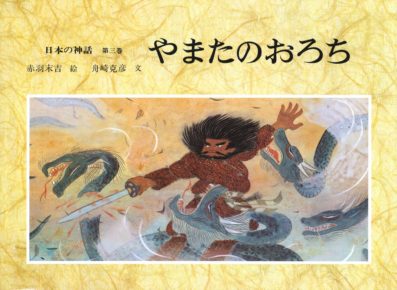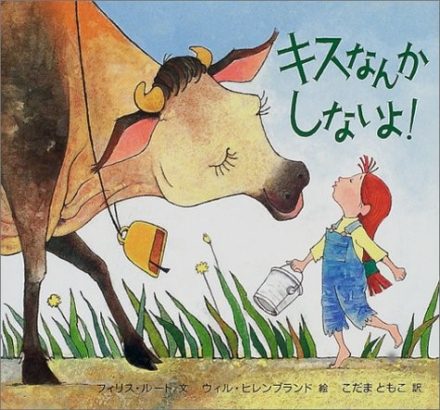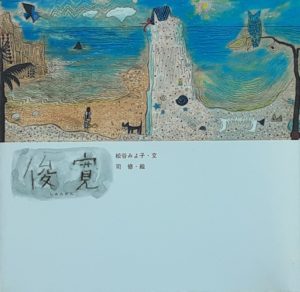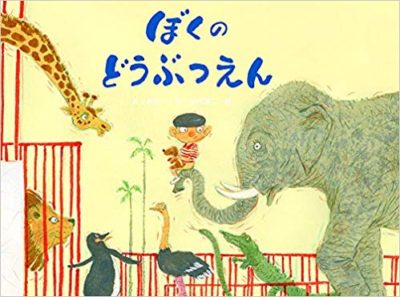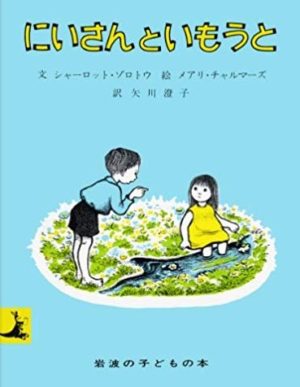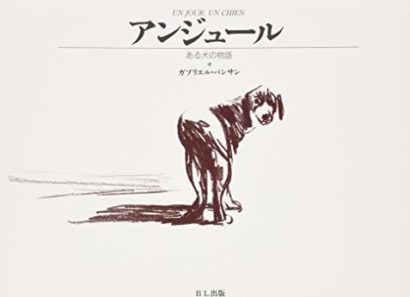
Ⅰ.絵本の読みかたりとは何か
絵本の《読みかたり》は、読み手と子どもたちがひとつの芸術世界のなかで、ともに呼吸し、生活し、体験することである。
ふかい思いをこめたいろどり豊かな言葉と絵によって描きだされる世界のなかで、子どもたちは、想像力をはばたかせ、ゆたかなイメージを思いえがくことができる。
子どもたちは、おはなしの世界を生きる人物とひとつになって、作中人物の喜びを喜びとし、悲しみを悲しみとする同化体験をするとともに、またその人物を外から見たり、一歩身をひいて考えたり、さらには批判的な目をむけたりするような体験もしていくことであろう。
場面の展開にしたがって、子どもたちは、次の場面を予想し期待して想像力をいきいきと働かせることになるが、このようなイメージの体験が、 子どもの中にひきおこす想像と思考の触発力はとても大切なことである。おもしろがって、ページをめくるなかで、子どもたち自身が、自問自答しながら、思考、想像の力をみずから引きだし育てているといえるであろう。
絵本の世界の体験は、想像力を養い、思いやりの心を育てる体験である。
「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に見えないんだよ」 サン=テグジュペリ『星の王子さま』
また、子どもたちは、作家の目をとおして、具体的なイメージによって、さまざまな真実、真理、価値、美というものを認識することができる。日常の生活で体験してはいるけれども、わたしたちはその中にある意味については深く考えていないことが多い。絵本の体験は、深く切実なイメージの体験することを通して、自分とまわりの世界を見直す目を育てることになるであろう。
子どもたちの胸に強く訴え、その心をゆさぶる感動を通して、人間の行動や人間の心について理解する。それは、けっしてお説教ではなく、子どもたちが面白く楽しく体験することのなかではたされるものである。
「こころが今日知ったことを、頭が明日理解する」
(J.スティーブンス)
絵本の読みかたりは、このように子どもたちの心のなかにすばらしい種子をまく仕事である。子どもたちは、絵本を読んでもらった体験を思い返し、考えを深めていくことによって、いつか必ず、その体験の深い意味をさぐりあて、また自ら生みだしていくことであろう。
Ⅱ.読みかたりの方法-心を込めての読みかたりが子どもの感動を呼ぶ
絵本を読みかたるということは、おはなしに生命を吹きこむことであり、絵本の世界との対話、子どもと読み手との対話である。読むのではなく、絵本の世界を子どもたちに語りかけるように。
おはなしや絵本を読みかたる場の雰囲気、共同の意識、読み手の人間味、声の表情、顔や身体の表情、調子、声量、テンポ、強弱、間、呼吸、イントネーション等に気を配って、子どもたちと一緒に絵本の世界を生き生きと体験することがたいせつである。
「眠っている言葉を起こして動き回らせること」
(アイリーン・コルウェル)
1. 説明読みと表現読み
説明読み-子どもに読みかたりながら、書いてあることがらや言葉の意味などを、ある程度補ったり、説明をつけ加えたりしながら読んでやる読み方。
表現読み-場面のイメージを大切にして、つまりこの場面がどのようなイメージなのか、恐ろしいイメージの所か、あたたかいイメージの所か、めまぐるしく転変するイメージの所かなどをつかんで、それらをあらわすような声量、テンポ、強弱、間、イントネーション等を工夫して読む読み方。
2《読みかたり》のねらい
・えがかせる
・ かんじさせる
・かんがえさせる
「えがく」「かんじる」「かんがえる」のねらいを場面によって使い分けること。また。「えがく」ことが「かんじさせる」ことであり、「かんじる」ことが「かんがえる」に繋がる。これらの「ねらい」は相互にかかわり合っている。
3《読みかたり》の方法
①.読み手の基本的態度
《読みかたり》は、それ自身で成り立っているのではなく、聞き手である子どもたちを考慮に入れて、子どもたちの受け取り方を前提にして成り立っている世界である。子どもたちにどのようなイメージをつくらせ、どのような体験をさせるのか、そのねらいによって、《読みかたり》の仕方もちがったものになる。また、作品には〈はじめ〉から〈おわり〉まで、ひとつの流れがあり、めりはりがあり、緩急があるということに注意すること。
②.基本的なトーン-ことばは音声のなかでいきている
はりのある声
しずかな落ち着いた声
たのしいうきうきした声
かなしいしずんだ声などを使い分ける。
③.イントネーション
絵本のそれぞれの場面における登場人物の性格や気分、その行動に対する読み手の評価や態度をあらわすのに、様々なイントネーションの使い分けが必要である。かなしさ、うれしさ、ずるがしこさ、すなおさ、うたがわしさ、力づよさ、のどかさ、あわただしさ、おもしろさ・・・・など、多様な使い分けが作品のゆたかさを引きだす。
④.〈間〉のとり方
意味的な〈間〉 Ⅰ.テキストに指定された意味的な〈間〉
Ⅱ.読み手がつくる意味的な〈間〉
心理的な〈間〉 Ⅲ.テキストに指定された心理的な〈間〉
Ⅳ.読み手がつくる心理的な〈間〉
⑤.読みのテンポ
ゆっくりしたテンポ、はやいテンポを場面によって使い分ける。登場人物の性格によって、そのせりふや行動を語るときのテンポを使い分けるとおもしろい。例えば「くま」のせりふはゆっくり、「うさぎ」のせりふはいくらか速くというように。
さらに人物の気分によってテンポを使い分けることもおもしろい。よろこびや楽しさ、いきいきとした気分の時は速く、悲しみ、さびしさ、なげき、考えこんだり、うたがったりする時はゆっくりと。一本調子ではなく、めりはりをつけて読むことがコツ。
⑥.読み手の姿勢、顔つき、手つき、身ぶり
絵本を相手にむかって語りかける、話しかけるというのが基本。表情、身ぶり、手ぶりはほどほどにして、 主役は読み手の「声」であることに注意する。
Ⅲ. 絵本の選びかた
1.のぞましい体験と知識
体験を媒介にして認識が変革され深められ、結果として子どもたちのなかに人間やものごとについての正しく広い知識が形成されるような絵本。
2.のぞましい主題
子どもたちにとって避けなければならないテーマ(主題)は、原則的にいってない。テーマは多様。
3.のぞましい人間像
人物像が明確であること。性格がすっきりしていること。肯定的な人物像を中心に(幼児・低学年の子ども=善悪のパターンによって認識する)
4.芸術的な絵本
芸術的な絵本とは何かというのは難しいことです。 多様な美を意識して、 あなたの審美眼から絵本を選んで下さい。
(2021/10/17)