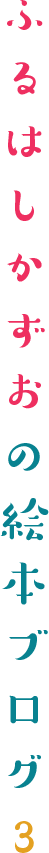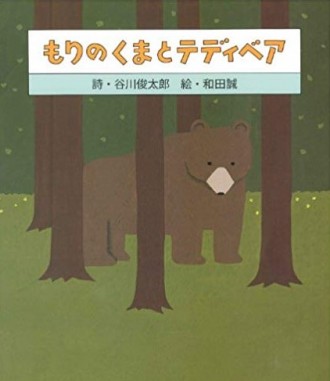新美南吉の名作「ごんぎつね」です。
悲劇的な物語です。
・・・
「ごんぎつね」の語り手は、ごんによりそって語っていきます。ごんの心が手に取るようにわかります。今回はそのストーリーの紹介ではなく、兵十に撃たれて死ぬ最後の場面で、視点がごんから兵十の側に切りかわりますが、この視点の転換についての考察です。すこし長くなりますが、その場面を引用します。
・・・
そのあくる日もごんは、栗をもって、兵十の家へ出かけました。兵十は物置で縄なわをなっていました。それでごんは家の裏口から、こっそり中へはいりました。
そのとき兵十は、ふと顔を上げました。と、きつねがうちの中へ入ったではありませんか。こないだ、うなぎをぬすみやがったあのごんぎつねめが、またいたずらをしに来たな。
「ようし。」
兵十は立ち上がって、なやにかけてある火なわじゅうを取って、火薬をつめました。そして、足音をしのばせて近よって、今、戸口を出ようとするごんを、ドンとうちました。
ごんは、ばたりとたおれました。
兵十はかけよってきました。うちの中を見ると、土間にくりが固めて置いてあるのが、目につきました。
「おや。」と、兵十はびっくりして、ごんに目を落としました。
「ごん、おまえだったのか、いつも、くりをくれたのは。」
ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。
兵十は、ひなわじゅうをばたりと取り落としました。青いけむりが、まだつつ口から細く出ていました。(ゴシック体は引用者)
・・・
視点の転換
「そのとき」以降、語り手の視点はごんから兵十に変わりました。語り手は兵十の目とこころに入って語っています。兵十の言葉に見えるところ(こないだ、うなぎを……またいたずらをしに来たな。)に「 」がなく語り手の言葉として書かれています。読者は兵十の心の中がわかります。兵十の立場に立たされます。
兵十から見れば、ごんは「きつね」であり「あのごんぎつねめ」です。また、「土間にくりが固めて置いてある」と描写されています。この描写は、兵十の視点だからこそ可能な表現です。そして、「青いけむり」はごんの死を悼む香華のようです。
・・・
なぜ、ここで視点が転換するのでしょうか。
ここまで、ごんを身近に感じていた読者がいます。そのとき兵十がゴンに気づき「火なわじゅうを取って、火薬をつめました」。この危機的な場面に出会い、読者には「 兵十、撃ってはだめ !」というドラマチックな体験がうまれることでしょう。
また、この視点転換は、ごんの悲劇に加え、「ひなわじゅうをばたりと取り落とし」た 兵十の悲劇を浮きぼりにします。ひとりぼっちのごんと兵十。最後まで、ふたりは心が通じ合う関係にはなりませんでした。ゴンと兵十のディスコミュニケーションは、いまもある人間関係のすがたです。南吉が身近に見ていた人間関係の状況だったのではないかと推測します。
起こってはならない悲劇です。なぜ、それが起ってしまったのでしょうか? この場面の視点転換によって、読者の体験を深め、この悲劇の原因は何かという「問い」が読者に提示されています。
・・・
※『 ごんぎつね 』 新美南吉、 黒井健絵、 偕成社 1986

【 追記 】
南吉は「かげ」という作品でも視点転換の方法を用いています。自分の影と競争し死んだからす。最後の場面で語り手は言います。「つぎの あさ、 もりへ 木を きりにいった 木こりが、 もりのそばの くさはらのうえに、 からすが 一わしんでいるのを見ました」。からすに寄り添う語り手の視点から、からすの死を伝える客観的な語り手の視点に変わっています。この視点転換によって、読者はからすの死の意味について考えざるをえなくなります。作者の「問い」を提示する視点転換です。
「かげ」はこのブログで紹介していますので、ご覧いただければ幸いです。
新美南吉の写真は、愛知県半田市にある「新美南吉記念館」の展示パネルを撮したものです。