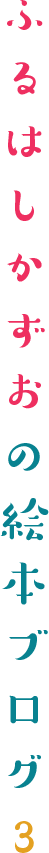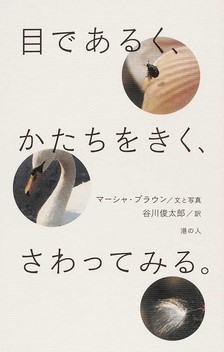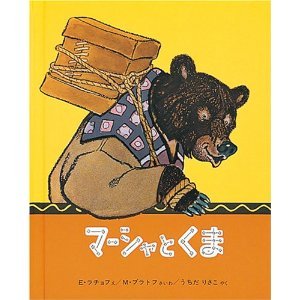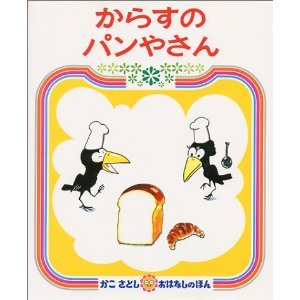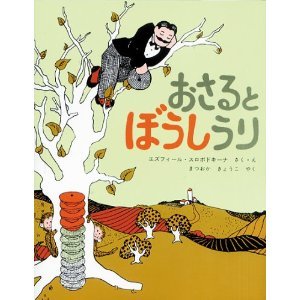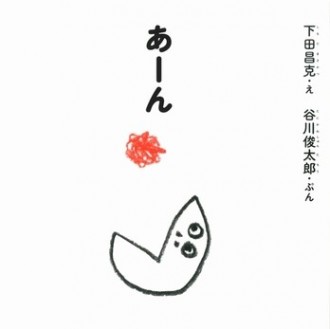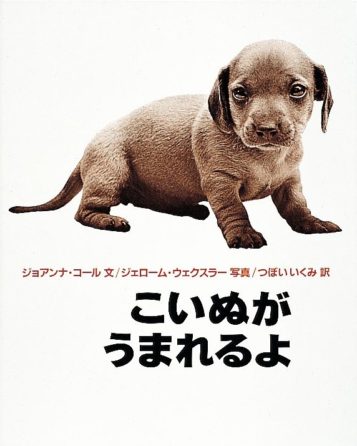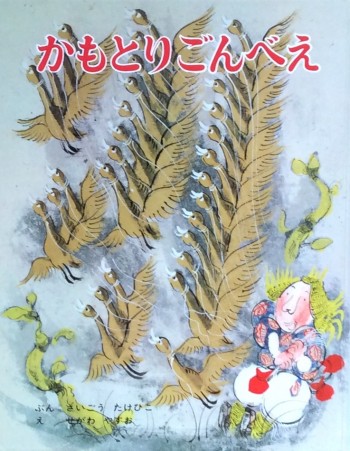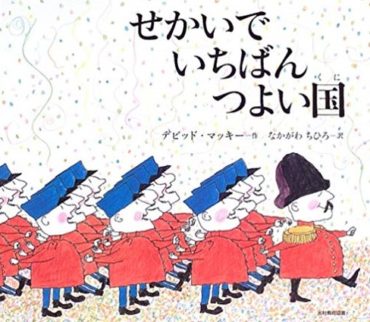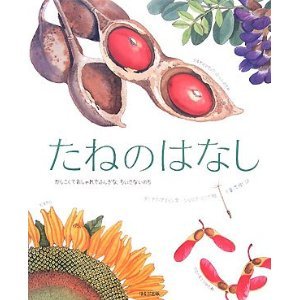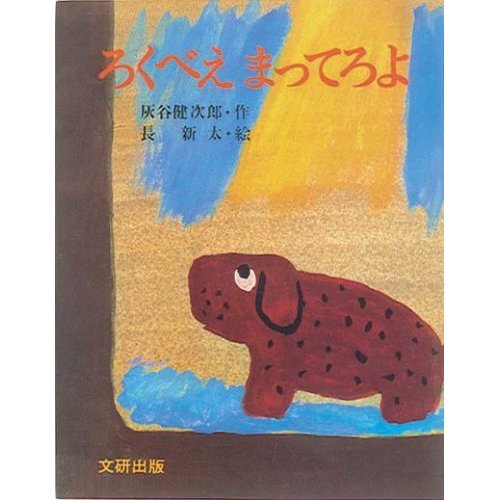
深い穴に、ろくべえ (写真の犬) が落ちてしまいました。
泣き声で ろくべえとわかりますが、 姿はみえません。
かんちゃん
みすずちゃん
えいじくん
みつおくん
しろうくん
5人の子どもたちが、
自分たちの知恵と力で、ろくべえを救出するというおはなしです。
・・・
子どもたちは、最初から、ろくべえを 救いたい 気持ちでいっぱいです。
でも、救出の方法が 分かりません。
前半の子どもたちは、
声援したり、
歌をうたったり、
シャボン玉を吹いてあげたりしています。
おとなにも頼りますが、
おとなたちは無責任にも、その場を立ち去ってしまいます。
( このあたりは、 わたしの少し不満なところです。 おとなが無責任すぎるのです。)
・・・
誰も あてにできないと わかった子どもたちは、自分たちだけで 助けようと思い、頭が 痛くなるほど 考えます。そして、ろくべえの 恋人のクッキーという犬を、かごの中に入れ、 穴におろすアイディア ( 「こうすること」 )を思いつきました。そうすれば、クッキーの乗ったかごに、ろくべえもいっしょに 乗るだろう ( 「 こうなること 」 )と予想しました。そこを ひきあげる というわけです。
めいあん。
めいあん。
・・・
「こうすること」 ( 能動 ) と
「こうなること」 ( 受動 ) のむすびつきがわかりました。
少し大げさにいいますと、まだ実現していない予想であり仮説です。
・・・
そのあと、子どもたちは、予想を意図に転換して、「 こうなる 」ようにという意図 ( 目的 )をもって、「 こうする 」姿を示しています。活動は、未来 ( 「こうなること」)を含む現在の活動 ( 「 こうすること 」 )となりました。その途中、ちょっと ハッとするところも ありますが、最後は、見事救出。みんなは大喜びです。子どもたちの 救出劇は、 こころのこもった 目的のある 経験となりました。
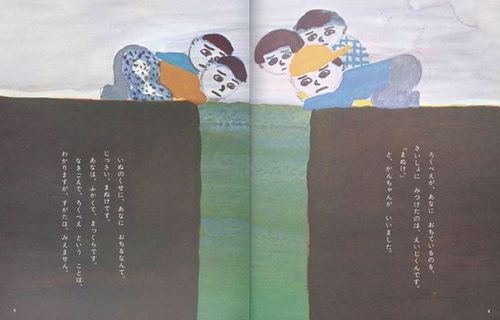
経験が、順調な経過をたどって、その完成に達するとき、私たちはひとつの経験をするのである。 そのとき、そしてそのような場合にのみ、経験は内面的に統合され、経験全体のなかで、ほかの経験から区別される。
・・・
アメリカの哲学者・教育学者のデューイの言葉です。
デューイのいう 「 ひとつの経験 」 には、
まとまり
個性的な性質
自己充実性があります。
子どもが遊びなどにおいて、目的を達成したとき、こころから満足し、自信をつけ、充実感を あじわうことでしょう。そして、その活動について、さまざまに意味づけていくことでしょう。また、そのなかには、 興味や関心をひろげ、意志を訓練する機会があることでしょう。『 ろくべえまってろよ 』 の子どもたちの経験のように。
この絵本は、「 ひとつの経験をする 」すがたを描いた絵本でもあります。
・・・
※『 ろくべえ まってろよ 』 灰谷健次郎作、 長新太絵、 文研出版 1978年 (2013/8/6)