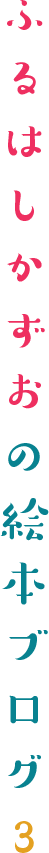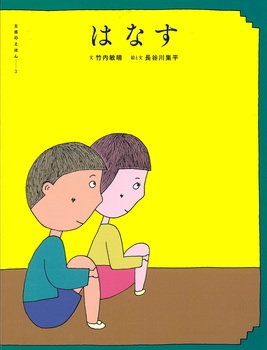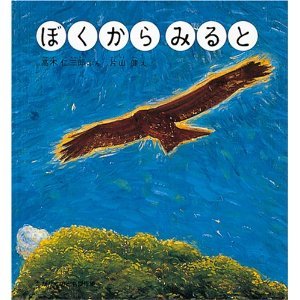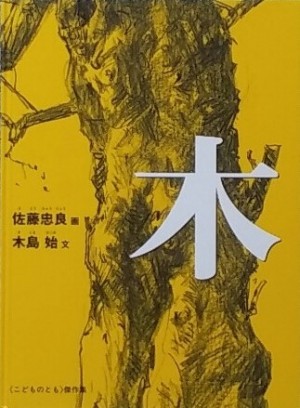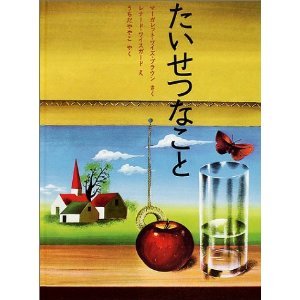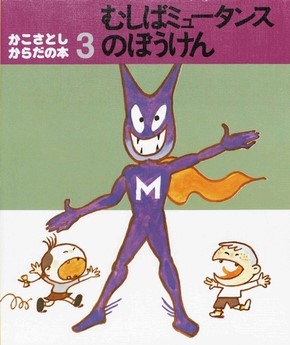
語り手についての考察です。
絵本の中にもさまざまな語り手が出てきます。長谷川摂子さんの絵本の『さくら』は、文字通り桜の木が語り手です。かこ・さとしさんの『 むしば ミュータンスの ぼうけん 』は、虫歯の原因であるミュータンス菌が語り手になっています。ミュータンスが「わし」と言ってでてきます。斎藤隆介さんの『花さき山』の語り手は「おどろくんでない、おらは この山に ひとりで すんでる ばばだ」と言う「山ンば」です。
今回は、この語り手をテーマにして、ユニークな語り手が設定されている3つの詩を例に表現の面白さと詩の虚構性について考えます。はじめは、宮入黎子さんの詩「から」です。
から 宮入黎子
ザリガニが
すぽっと からをぬいだんだ
赤い じょうぶな から
着なれたやつ
田んぼのどろの しみたやつ
今
やわらかい 白い体なんだ
からをぬぐって
どんな気持ちだろう
ぬぎすてるたび
大きくなる ザリガニ
ぼくにも からがあったら
バリバリ ぬぐ
おとなになって どこへでも行く
詩の語り手は「ぼく」です。 しかし、 作者はといえば、宮入黎子という女性の詩人です。なぜ 語り手は「ぼく」なのでしょうか。語り手を「ぼく」に設定した意味について考えなければなりません。「から」の詩に描かれている対象は、ザリガニのたくましい成長ぶりとそれに共感している少年の「ぼく」の思いです。ザリガニの形象は、男の子の語り手の口調(文体)とひびきあい、成り立つものであるといえます。野性的なたくましいザリガニの形象とひびきあう〈ぼく〉の形象は、〈ぼくにも からがあったら/バリバリ ぬぐ〉〈おとなになって どこへでも行く〉ところに典型的にあらわれています。
さて、〈ぼく〉の殻というのは、親や教師が子どもを守るために外側から着せているものだと言えます。そのために子どもの身が守られていますが、 子どもからするとやはり窮屈です。何か自分のしたいことができないということでもあります。〈ぼくにも からがあったら/バリバリぬぐ/おとなになって どこへでも行く〉というのは〈ぼく〉の気持ちです。このようなテーマが、〈ぼく〉の視点、〈ぼく〉という語り手の設定によって成功していると言えるでしょう。
おと いけしずこ(工藤直子)
ぽちゃん ぽちょん
ちゅび じゃぶ
ざぶん ばしゃ
ぴち ちょん
ざざ だぶ
ぱしゅ ぽしょ
たぷん ぷく
ぽつ どぼん・・・
わたしは
いろんな おとがする
〈ぽちゃん〉〈ぽちょん〉〈じゃぶ〉〈ざぶん〉〈ばしゃ〉- これらの音は、池がさまざまなものと出会うことによって、それぞれにあった音をたてている様子を表現しています。〈おとがする〉とあるが「おとをだす」と言ってもよい。水がさまざまな相を現わすことを音だけで書いています。
また、〈・・・〉は何かといえば、ほかにもいろいろたくさんの音があるということです。〈わたし〉はどんなものとでも〈おと〉をだす。極端にいえば無限に考えられると言っています。この無音の〈・・・〉は何も書かれていませんが、イメージと意味をゆたかにひき出すことのできるところです。
さて、この詩の〈わたし〉とは一体だれでなのでしょうか。「おと」の作者が「いけしずこ」となっていることを考えると、この〈わたし〉は「いけしずこ」(池)であることがわかります。語り手は〈いけ〉(水)です。
語り手は「水」ですが、主題はもちろん人間のことです。この〈いけ〉の形象は人間のたとえなのです。人間の問題として考えてみれば、人間の可能性について言っているではないかと意味づけることができます。〈わたし〉は縁によって、条件によってさまざまな姿、相(音)を現わすと言っています。人間というものは、他者と出会い、いろいろなものとの関係において、自分の可能性をさまざまに実現しています。そこに人間のすばらしさがあります。人間のゆたかさというのは無限の可能性を秘めているということです。それは、まるでこの〈いけ〉がさまざまな物と出会って、それぞれにあった音を出すことと同様です。
この作品は「人間というものは、出会いによって無限の可能性にむけて開かれている存在である」という人間の真実が、〈いけ〉という題材を使っておもしろい形で(美として)表現されています。
また、文芸(詩)の意味づけについて言えば、池に向かって石を投げ込み、うまれるさまざまな〈おと〉に似ています。美しい音をだすのかどうかは、自分の解釈、意味づけにあります。意味は詩の中にあるのではありません。意味づけるということは、いくらでも可能です。〈いけ〉の中に石をどのように投げ込むか、投げ込み方もいろいろあるでしょう。意味づけというのは無限に可能なのです。古典の永遠性、古典の解釈の多様性というのは、このような虚構の性質によっているといえます。
また、同じことですが、虚構というのは〈わたし〉が作品に投げ込んでできる〈おと〉なのです。〈おと〉はものと池の関係から生まれる現象です。この〈おと〉が、虚構なのです。〈音〉が〈いけ〉の中にないように、虚構(意味、価値、美 )も作品の中あるのではありません、読者がどのように読むか(どのような石を池の中にどのように投げ込むか)によって、さまざまな読み(意味、価値、美-音)が生まれます。作者の主体性、読者の主体性ということは、このことだと思います。
せみ 有馬敲
じぶん じぶん じぶん
じぶん じぶん じぶん
じぶん じぶん じぶん
じぶん じぶん じぶん
じかーん じかーん じかーん
じかーん じかーん じかーん
じかーん じかーん じかーん
じかーん じかーん じかーん
じゆう じゆう じゆう
じゆう じゆう じゆう
じゆう じゆう じゆう
じゆう じゆう じゆう
この詩の語り手(視点)は〈せみ〉である。その〈せみ〉が誰かに向かって〈じぶん じぶん〉と言っている。不特定多数のまわりの者(聞き手)に対して〈じぶん じぶん〉と言いたてています。また、〈じかーん じかーん じかーん〉(時間)がないとか、足りないとか、欲しいとか言っています。〈じゆう〉(自由)をくれ、〈じゆう〉が欲しいと訴えています。〈じぶん〉(自分)〈じかーん〉(時間)〈じゆう〉(自由)は、〈せみ〉の鳴き声とこれらの漢語の意味をかけた表現、掛詞的な表現です。
〈せみ〉(蝉)は地中で生きている時間がはるかに長い。何年も土の中にいて、ある年地上にでてきます。そして一週間か十日ぐらいの間、精一杯鳴いて、メスを求めて次の世代へ自分のいのちを譲ってはかなく消えていきます。だから〈せみ〉は必死に短い残された人生を精一杯〈じぶん じぶん じぶん〉とか〈じかーん じかーん じかーん〉〈じゆう じゆう じゆう〉と自己主張して生きているのです。生きる目的があってしていることです。このような〈せみ〉の気持ちは、読者が同化体験をするとよくわかります。読者は聞き手に同化して、聞き手と一緒になって〈せみ〉の言い分を聞く。語り手である〈せみ〉と一緒になって語り手の気持ちになって「ああ、〈じぶん じぶん〉という気持ちはわかる」「時間が足りないというのはよく言うことだなあ」というふうに、〈せみ〉に同化して読んでいく。
一方、読者は外側から脇から横から〈せみ〉を見ると、何ともうるさい限りで、いい加減にしてほしいという感じになるのではないでしょうか。暑苦しい夏に、しかも暑苦しい声で鳴きわめく〈せみ〉に対してうるさいという感じです。聞き手の側にまわって〈せみ〉の言い分を聞いていると、なんだか自分本位だなあというふうに、すこし批判的に見るという体験をします。
さて、この詩の諷刺について述べておくとすると、〈じぶん じぶん じぶん〉〈じかーん じかーん じかーん〉〈じゆう じゆう じゆう〉という表現は、わかりやすく言えば、気ままな自分の自由だけを言い立てていると考えてもよい。これは視点を〈せみ〉に置き、〈せみ〉を語り手にした、また〈せみ〉だからこそこのような詩ができたのである。ほかならぬ〈せみ〉という題材を用いて、自己主張(自己中心のエゴイズム)というもののもつ滑稽さをおもしろく表現している詩である。ある種の人間の生きざまを諷刺して〈せみ〉に託して描いています。
〈せみ〉本人はせつないぐらいに精一杯鳴きたてていますが、第三者の目から見ると暑苦しい、うるさい、たまらないというような感じになります。ある意味、イメージの二重性、二重の体験をします。異質な矛盾する体験を表裏一体のようにして体験する。これが美の体験であり、詩を読むことでえられる豊かな体験ということです。矛盾する読みが同時に成立します。これが虚構の世界のおもしろさということです。
3つの詩を例にして、語り手の設定の意味と表現の面白さ、また虚構性について考えてみました。 (2022/3/8)