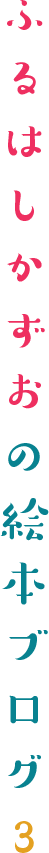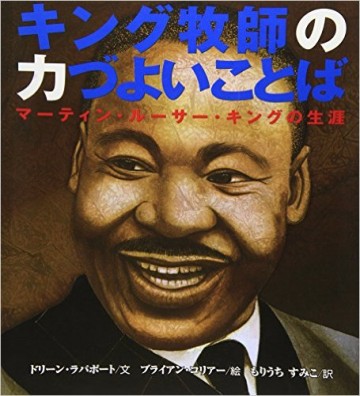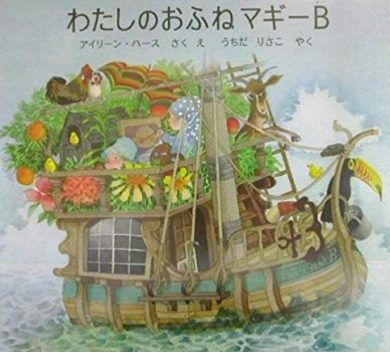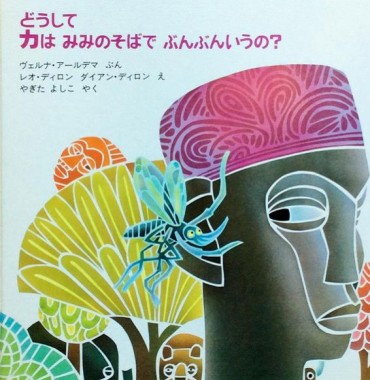きつねが こがもを食べようとして、
秋、冬、春と3度失敗するおはなしです。
語り手の視点は、きつねの側にあります。
なぜ、視点をずるい きつねの側に置いたのでしょうか?
今回は、視点と読者の体験の考察です。
・・・
秋。
かもが 旅じたくをはじめました。
きつねが 考えます。
どうれ、川へでかけて、
こがもを つかまえてやろう。
まるまると 太っているだろうと きつねは考えているのです。
つぎの場面から、語り手の言葉ですが、語り手はきつねの側にありますので、きつねの心を想像して( )のなかに書いてみます。
かんぼくの かげから、そっとのぞくと、おもったとおり。
いるわ いるわ かわぎしに かもが せいぞろいです。
( しめしめ。いまにみてろよ。 )
いちわの こがもが、ちょうど かんぼくの すぐしたで、
つばさの はねを そろえていました。
( のんびりと 翼のはねを そろえてるぞ。よし、あいつにしよう。)
・・・
きつねから見た こがものイメージです。
こちらに きつね。
あちらに こがも。
イメージに遠近感が あります。
読者は、きつねに同化していきます。スリルの ある体験です。
( 絵本の絵は、こがもの側に視点を置いています。文章と絵の視点が異なっています。下の絵。 )
冬。
ここでも、きつねの側から、こがもは見られています。
でも、
また失敗。
春。
あたらしい羽がはえた こがも。
きつねから逃れ、さっと飛びさっていきました。失敗から学んだこがも。こがもは成長したのです。

視点は、ずるいきつねの側におかれていました。この視点によって、スリルのある体験がうまれます。読者の体験に緊張感があります。反対に、語り手の視点を、こがもの側に置いたらどうなるのでしょうか?
読者の体験から考えてみましょう。こがも側に視点を置いて、書き直してみてくだい。こがも側から見ると、不意にあらわれるきつねにびっくりしますが、原作のもつ緊張感やスリル感がなくなります。
でも、ずるいきつねの側に視点を置いてもいいの? という声が聞こえてきそうです。読者は、確かにきつねに寄りそう体験をするかもしれません。しかし、読者はきつねではありません。読者は読者。おはなしが進むにしたがって、あるいは読後に、きつねを批判的に見ることになるでしょう。やっぱり、そうはいかないよ、いい気味だというように。
視点、
イメージの遠近、
読者の体験は、密接に関連しています。
・・・
※『 かもと きつね 』 ビアンキ作 、 内田莉莎子訳、 山田三郎画、 福音館書店 1962年
【追記】
今回の絵本の紹介は、文芸学者・西郷竹彦氏(1920-2017)の論考に基づいています。視点、イメージの遠近、読者の体験を結びつけた西郷竹彦氏の理論は、絵本を分析するうえで、また絵本を読みかたるうえでおおきな示唆をあたえるものです。詳しくは『 西郷竹彦文芸教育著作集 7 』(明治図書)をご覧下さい。個人的なことですが、西郷竹彦氏の文芸教育の理論から私は多くのことを学びました。また、西郷氏の晩年、親しくお話する機会を幾度となく持てたことは私の貴重な財産です。
「ふるはしかずおの絵本ブログ3」は今回で500回になりました。 (2020/2/27)